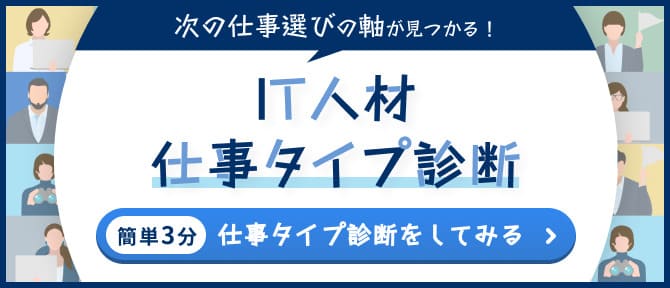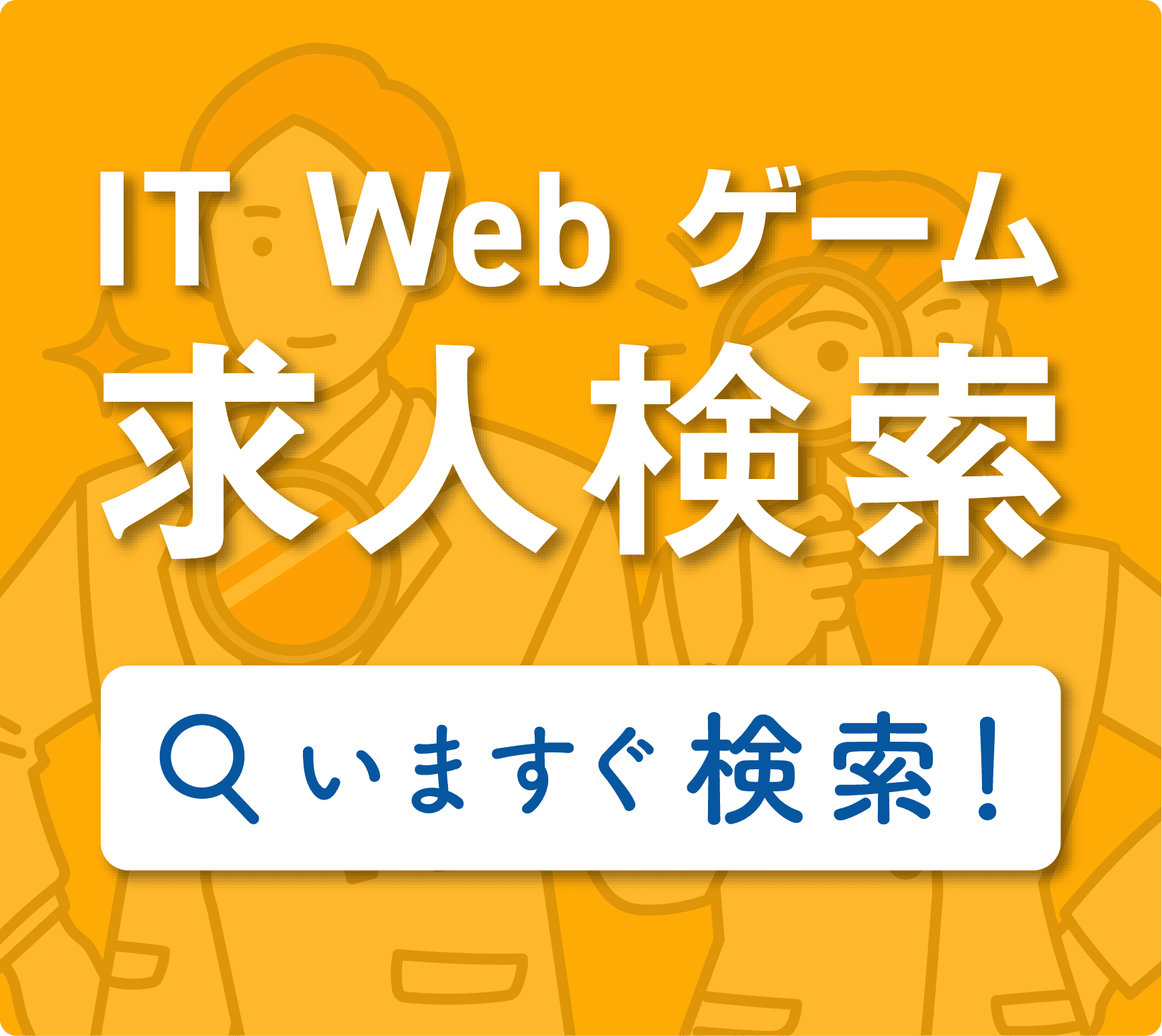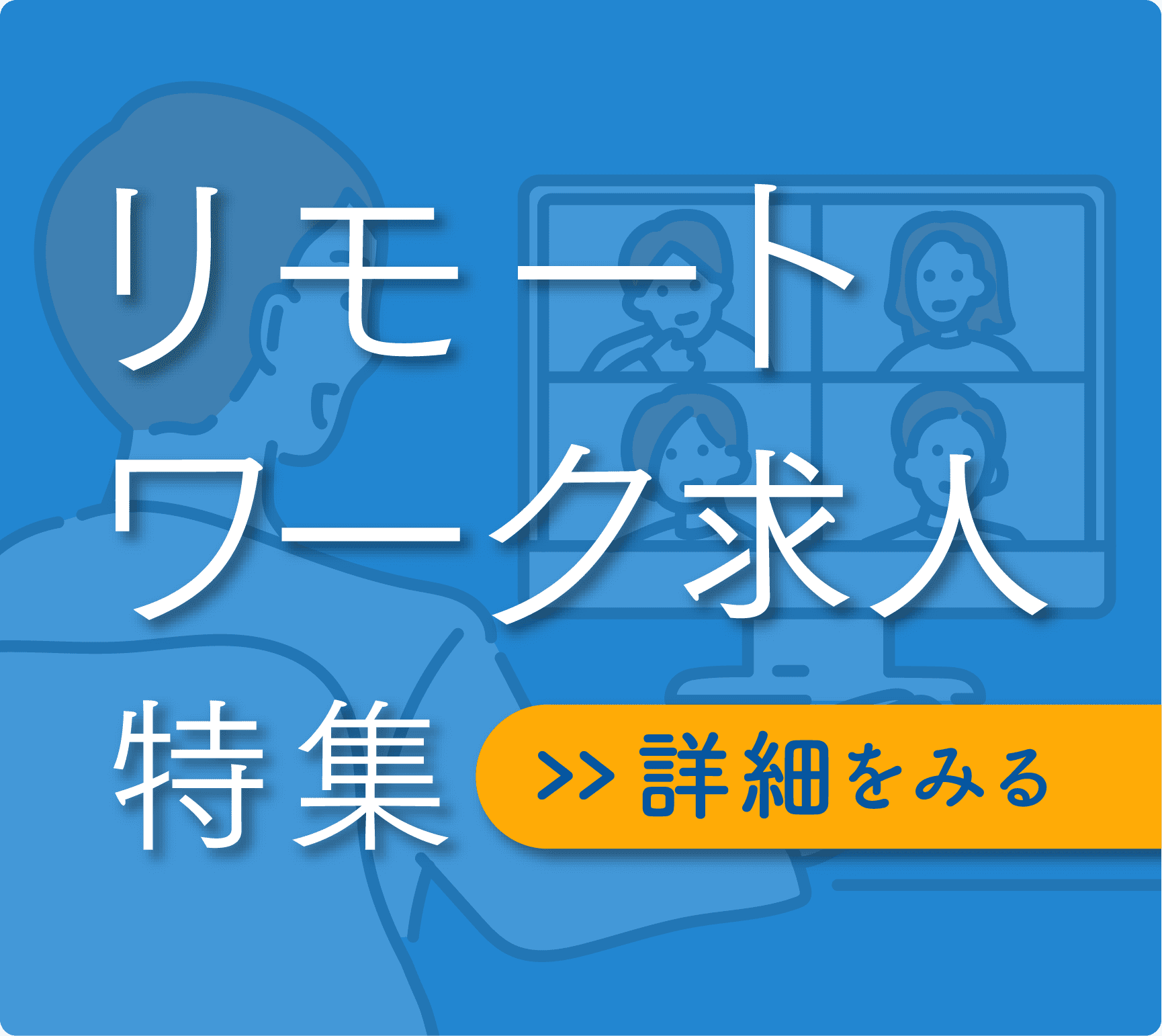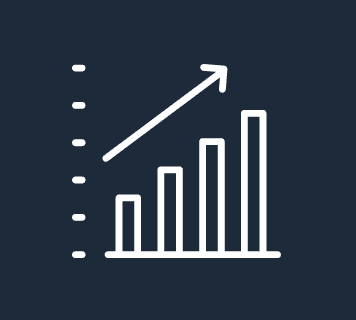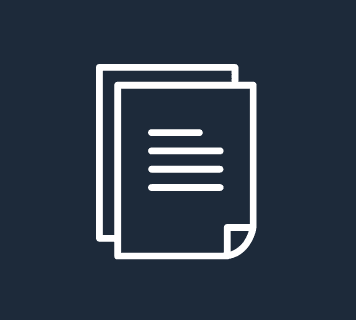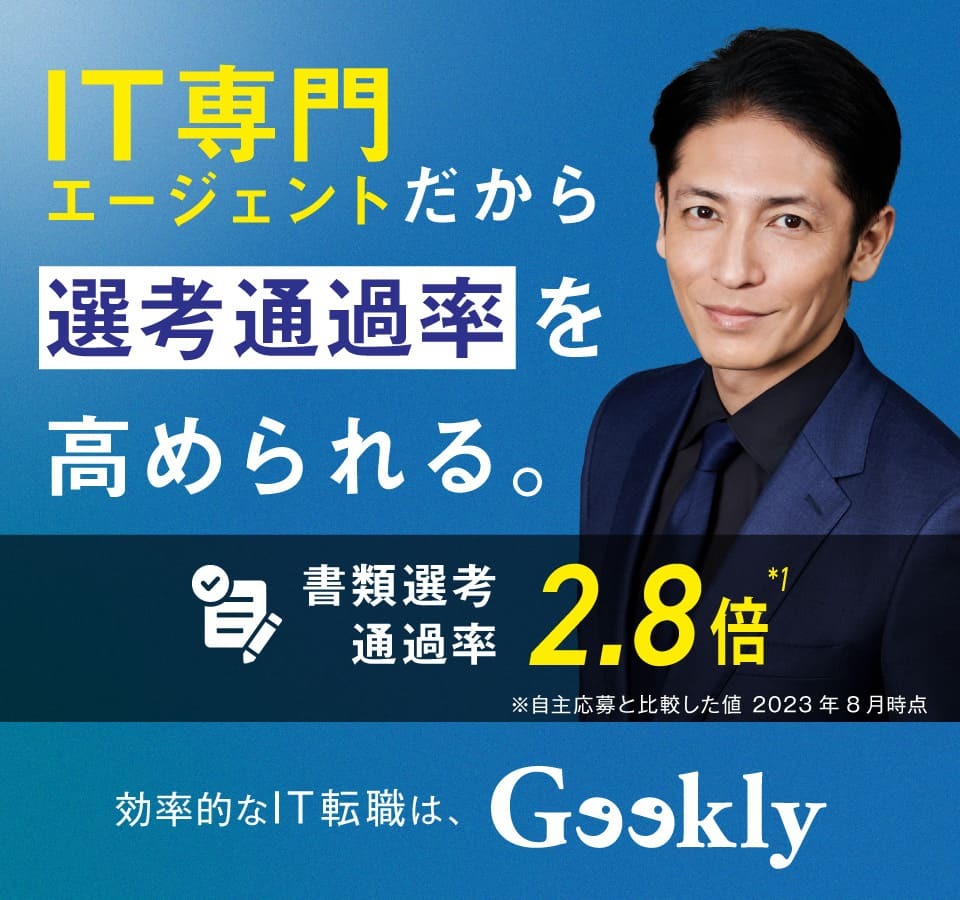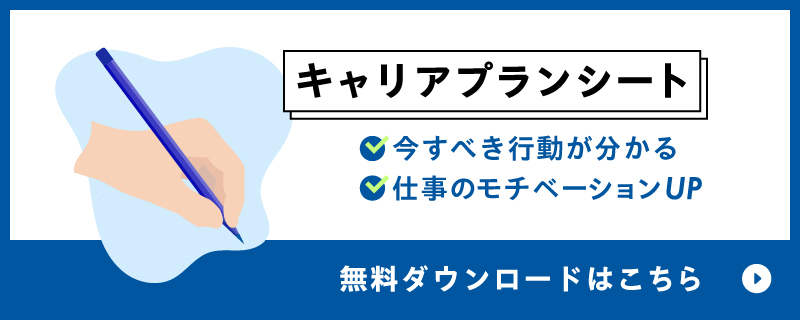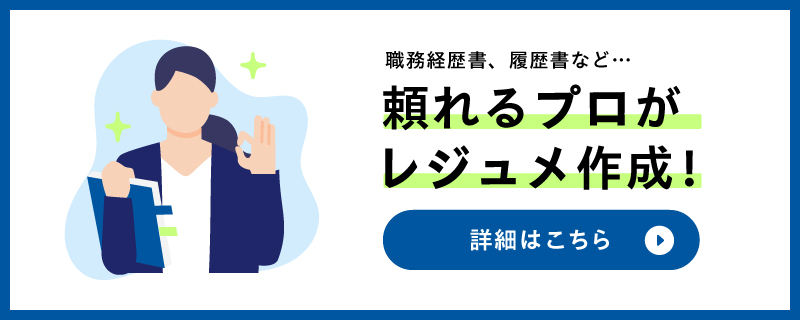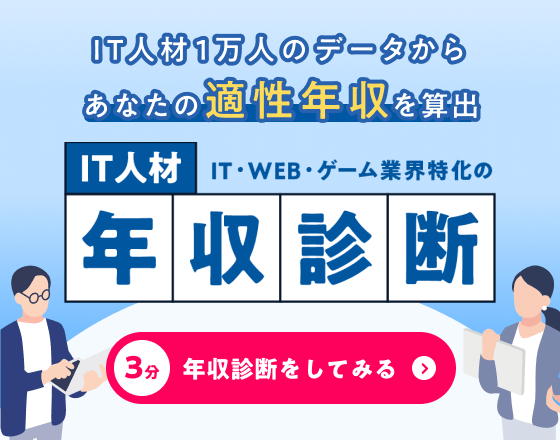ソーシャルゲームとは?意味やスマホゲームとの違い、仕組みを分かりやすく解説!
「ソシャゲ」という言葉を聞いたことがある人は多いのではないでしょうか?ゲームにはさまざまな種類がありますが、今回は近年増えてきているソーシャルゲーム(ソシャゲ)について、スマホゲームとの違いや意味、代表例、仕組みなどを紹介していきます。
目次
ソーシャルゲームとは
近年スマートフォンの普及とともにソーシャルメディアが急激に成長を遂げました。そんなソーシャルメディアは、社会生活だけではなくビジネスにも必要不可欠なものとなってきています。
それはゲーム業界でも同じで、ソーシャルゲーム、いわゆる「ソシャゲ」というジャンルが大きく注目を集め、市場もどんどん拡大しているのです。
では、そんなソーシャルゲームとはどういうものなのでしょうか?
ソーシャルゲームって何?
ソーシャルゲームとは、プラットフォームがSNS(ソーシャルネットワークサービス)であるゲームのことです。
そのため、ソーシャルゲームをプレイするためには、まずLINEやFacebookなどそのゲームに対応したSNSに登録することが必要になります。
SNSをプラットフォームにしてゲームをすることによって、SNS上の名前やアバターをそのまま使って、友達をゲームに招待したりゲーム内で友達を作って一緒に遊ぶこともできます。
これが他のゲームとの大きな違いです。
個人で遊ぶというよりはユーザー同士で遊ぶという要素が強く、ランキングを競う・アイテムを奪い合う・トレードするなど収集要素が強いゲームが多い傾向にあります。
ソーシャルゲームの代表例一覧
- ポケモンGO
- Among Us
- モンスターストライク
- パズドラ
- メメントモリ
- エバーテイル
- 原神
【あわせて読みたい】ゲーム会社の売上・年収ランキングはこちらから⇓
ゲームアプリとの違い
ゲームアプリもソーシャルゲームと同様にスマートフォンの登場とともに急激に成長したゲームとして知られています。
両者が同じものであると思っている方も多いかもしれませんが、実は全く違うものです。
その違いは、プラットフォームがSNSにあるか、独立したアプリケーションかどうかです。
ソーシャルゲームはプラットフォームがSNSにあるので、オンライン上のSNSにアクセスしてプレイしますが、アプリゲームは端末に一つ一つのアプリケーションをダウンロードして遊びます。
アプリゲームはダウンロードするだけで簡単にプレイすることができ、コンシューマーゲームのようにゲーム専用機を購入する必要がありません。
消費者は手軽に低コストで遊ぶことができ、生産者側も流通コストや開発コストを抑えることができるので、双方のニーズにマッチし爆発的に市場が拡大したという訳です。
【あわせて読みたい】知っておきたいゲーム業界の基礎知識はこちらから⇓
オンラインゲームとブラウザゲーム
ソーシャルゲームはDeNA(ディーエヌエー)やGREE(グリー)などが参画し、2012年頃から一気に広まりました。しかしその判別はかなり複雑です。
ゲームにはソーシャルゲームとゲームアプリ、またコンシューマーゲーム以外にも種類があります。
たとえばオンラインゲームやブラウザゲームです。これらはソーシャルゲームと何が違うのでしょうか。
違いを説明していきます。
オンラインゲーム
オンラインゲームは、その名の通りネットワークを使用したゲームです。
たくさんのユーザーがバトルに参加するRPG系はMMO、スポーツの側面を持つゲームはeスポーツなど、ひとことにオンラインゲームといっても特徴ごとに様々な種類があります。
ソーシャルゲームはこのオンラインゲームの一種です。
オンラインゲームの中でも、プラットフォームがSNSになっているものがソーシャルゲームにあたります。
ブラウザゲーム
ブラウザゲームはウェブブラウザを使用するゲームで、こちらもオンラインゲームの一種です。
ブラウザゲームはブラウザが使用できる環境であればプレイ可能で、アプリケーションをダウンロード・インストールする必要はありません。
一方、ソーシャルゲームはアプリケーションです。
アプリをインストールせずにブラウザを使用するのがブラウザゲーム、アプリのインストールが必要でプラットフォームがSNSならソーシャルゲームと覚えましょう。
ネイティブアプリとソーシャルゲームの違い
ネイティブアプリとは
ネイティブアプリとは、プラットフォームで直接動くアプリで、たとえばWindowsならWindows、スマートフォンならそのOS上で動作します。
MicrosoftのOffice(ExcelやWordなど)が有名なネイティブアプリです。
そして、ネイティブアプリのゲームももちろん存在します。
「ネイティブアプリのゲーム=ソーシャルゲーム」ではない
ネイティブアプリのゲームは、スマートフォン向けならもちろんスマートフォンで動作します。
ソーシャルゲームの拡大に伴い、スマートフォンのゲームはすべてソーシャルゲームと呼ばれがちです。
しかしながら、「ネイティブアプリのゲーム=ソーシャルゲーム」ではありません。
ネイティブアプリは直接端末上で動くので、ネット環境がなくても動作できます。
しかし、ソーシャルゲームは常にネット環境がないと動きません。それはプラットフォームがSNSだからです。
SNSはオンライン上にあるものなので、OSで動いているわけではないのです。
たとえば大ヒットしたスマートフォン向けの人気ゲーム「パズル&ドラゴンズ」も、厳密にはネイティブアプリのゲームです。
スマートフォン向けのゲームだからといって、必ずしもすべてのゲームがソーシャルゲームというわけではありません。
【あわせて読みたい】ゲーム好きが向いている仕事の一覧はこちらから⇓
ソーシャルゲームのメリットとデメリット
ソーシャルゲームのメリット
無料で遊べる
ソーシャルゲームの大きなメリットは、無料でダウンロードして遊ぶことができる点です。
アイテムなど課金できるものもありますが、基本プレイは無料でできる点がソーシャルゲームの最大の魅力だといえるでしょう。
手軽に遊べる
スマートフォンやタブレットといったモバイルデバイスで遊べる点もソーシャルゲームの特長です。
いつでもどこでも好きな時に好きな場所で遊べる手軽さは、無料でプレイできることに加えて大きな魅力です。
協力して遊べる
プラットフォームがSNSであるため、友達と一緒にプレイできます。
収集要素が強い特徴があるため、協力して進めたり、競い合う楽しみもソーシャルゲームの醍醐味です。
ソーシャルゲームのデメリット
依存性がある
手軽さ故に依存性が高いのもソーシャルゲームの特徴です。
ログインすることでもらえるボーナスや、続けなければ手に入らないアイテムなど、毎日続けてプレイする工夫がされています。
高額な課金をする場合がある
無料でダウンロードできる一方で、ステージを進めたりクリアにアイテム購入が必要なケースがあります。
課金を繰り返し、高額になってしまう可能性がある点は気をつけなければならないソーシャルゲームのデメリットです。
個人情報の流出の恐れがある
SNSと連動しているため、セキュリティに関する懸念もあります。
個人情報流出やゲーム内でのコミュニケーションによるトラブルにも注意が必要です。
ソーシャルゲームの課金システム
課金システム
- アバターやキャラクターのファッションアイテム購入
- ゲームをプレイするためのスタミナ回復
- ガチャを引くためのアイテム購入
- コンテニューするための課金
課金システムにはゲームをもっとプレイするための単純な自己満足の為だけではなく、おしゃれなファッションや強い敵を倒してライバルに自慢したい等、SNSを利用して友達に発信するゲームだからこその要素もあります。
また、最近ではプレイする度に課金するのが勿体ないという場合に対応するため、SNSの中で仮想コインを購入し課金ができる仕様もあります。
馴染みがあるアメーバやグリーは「コイン」、モバゲーなら「モバコイン」、ニコニコアプリなら「ニコニコポイント」など、様々な課金サービスシステムが存在するのです。
国別課金システム
このような課金システムは、制作する国によっても違う傾向がみられます。
例えば日本であったら色んなキャラクターなどを集める事にお金をかける傾向にあり、ガチャなどの課金システムが多い特徴があります。
アメリカはユーザー同士の勝敗を競うゲームが多く、勝負に有利に働くアイテムを購入するという課金システムが一般的です。
中国はお金を払えば払うだけ有利になるVIPシステムというものがあり、今までそのゲームでいくら使ったかという累計課金額が多い人ほど有利に働く仕組みがあります。
ソーシャルゲームが基本無料でプレイできる理由
基本プレイ無料
ソーシャルゲームをプレイしたことがある人は知っていると思いますが、ほとんどのゲームが基本的なプレイは無料となっており、最初にソフトを買う必要もありません。
では何故無料でプレイすることができるのでしょう?
それは追加要素として課金システムを採用しており、一部のプレイヤーが課金をする事で利益を得ているためです。
ソーシャルゲームは多くのタイトルにおいて受け入れ間口が広く、多くのプレイヤーを集客できるコンセプトで開発されることが多いため、ゲームのストーリーも簡単で短時間で楽しめる仕様になっています。
さらに、携帯電話やスマートフォン、ブラウザなど以前から普及している情報機器を使って展開することにより、複数のゲームユーザーにアプローチできます。
その上無料でプレイできるとあって、売上とシェアを同時に伸ばしているのです。
利益の仕組み
では、具体的にどのような仕組みで利益をあげているのでしょうか。
ソーシャルゲームの売り上げは、
で計算することができます。
DAUは一日にログインしたユーザー数、ARPPUは課金しているユーザーの月額支出額の平均を指しています。
つまり1日の売り上げは、
で計算することができます。
仮に3万人がプレイしており、課金率が5%で平均課金額が500円の場合
1日当たりの売り上げは75万円になるのです。
これを月間にすると2250万円稼げるという計算になります。
もちろんここから運営費などを引いた額が利益になるのですが、一回売ってしまったら終わりの家庭起用のゲームとは違い常に永続的な収益モデルを形成することが可能です。
そのうえ、開発費も家庭用ゲームと比べると一般的には抑えることができます。
ソーシャルゲームは収益モデルを作りやすいゲームであるといえます。
収益モデル4種類
ソーシャルゲームのマネタイズ方法は次の4種類です。
有料型
ゲームタイトルを有料で販売することで収益を発生させるモデルです。
主に、人気キャラクターが使用されたゲームや、過去作のリマスター版のようなすでに実績があるものが該当します。
初期投資が大きくなるものの、リリース後の運営の負担は少なくなります。
アプリ内課金型(無料)
日本のソーシャルゲームで最も多く見られるタイプで、無料でゲームを提供して、ゲームを進めるなかで課金が必要なタイミングを作り収益を得るモデルです。
課金システムの具体例についてはこの後詳しく解説しています。
広告付き無料型
ゲームを無料で提供して最後まで課金なしで遊ぶことができます。収益は、プレイ中に入れ込んだ広告から得ます。
主に簡易的に遊べるゲームに多いモデルです。
ユーザー数が増えやすいメリットと、広告が邪魔と感じて離脱されてしまう可能性を考慮しなければなりません。
広告付きアプリ内課金型(無料)
ゲームの提供は無料で、広告の表示と課金アイテムも用意されているモデルです。
収益が安定しやすいというメリットと、挿入する広告や魅力的な課金アイテムを用意するなどの工夫が求められます。
ソーシャルゲーム業界の現状と今後
日本国内の20~30代の男女へのアンケートによると、ソーシャルゲームへの課金額は「1万円以内」が最も多い約60%という結果となりました。
その一方で、第2位は「1万円〜5万円程度」と回答した約20%です。
そして5万円以上課金している人の合計も約20%である点も注目すべきでしょう。(参考:PR TIMES)
事実、アプリ上位ランキングに名を連ねるタイトルは月商が億を越えることもめずらしくありません。
しかしユーザーが実際に遊んでいるスマホゲームの平均数は平均3、4個とも言われています。
この3、4個に選ばれるゲームを作り出すのは簡単なことではないはずです。
ソーシャルゲーム業界の課題
ソーシャルゲーム業界では、これからも市場の拡大や最新テクノロジーの実装など追い風が多いでしょう。
VRやメタバースなどの広がりはソーシャルゲームにも進むことが考えられます。
特に日本はデジタルコンテンツへの課金に対する抵抗が少なく、1ヶ月あたりにアプリに課金する金額は約2,000円で、これは世界一とも言われているのです。
少子高齢化
課金額は年代により差がありますが、若いほど高いというデータもあります。
ところが日本の少子高齢化は進む一方で、ソーシャルゲームの主なユーザーと言える若年層が減り続けるということです。
社会問題
ソーシャルゲームは、身近で関わりやすいからこそ依存しやすいものでもあります。
その中毒性の高さから、社会問題と言われているゲーム依存症の一因になる可能性や、未成年ユーザーの高額な課金額を支払う保護者にとっての懸念にも目を向ける必要があるでしょう。
人材確保
海外の市場へ展開する場合は、ゲームの世界観も含めて文化的背景の違いに留意することが求められます。言語だけでなく海外の文化への深い理解が必須です。
IT領域の人材不足は依然として続いているため、人材確保も今後さらなる課題となるでしょう。
【あわせて読みたい】ゲーム業界の現在と将来についてはこちらから⇓
ソーシャルゲーム開発に携わろう
ソーシャルゲームとはどういうゲームなのか、お分かりいただけましたでしょうか。
- SNSをプラットフォームとしたゲーム
- 多くのゲームが無料でプレイでき、友達や世界中の人と気軽に遊ぶことができる
- イベントなどが定期的に行われるなどやりこみ要素も多く課金することでより楽しめる
ゲーム業界の中では、「身近にゲームを感じる生活」「いつの間にかゲームがある生活」を生み出す存在。また「ゲーム」という名のついたインタラクティブなコンテンツを体験できるユーザーを増やす存在として、まだまだ注目を浴びるでしょう。
そんなソーシャルゲームの開発に携わり、人びとに愛されるタイトルを創りたいと思っている方もいるのではないでしょうか。
弊社では、IT/Web/ゲーム業界の転職エージェントとして、そのようなゲーム業界への転職を考えている方や未経験からゲーム業界にチャレンジしようと思っている方の背中を後押しさせて頂いております。
非公開求人を含む10000件以上の求人をご用意しておりますので、少しでもご興味をお持ちの方は、お気軽にお声がけくださいませ。
あわせて読みたい関連記事
この記事を読んでいる人におすすめの記事