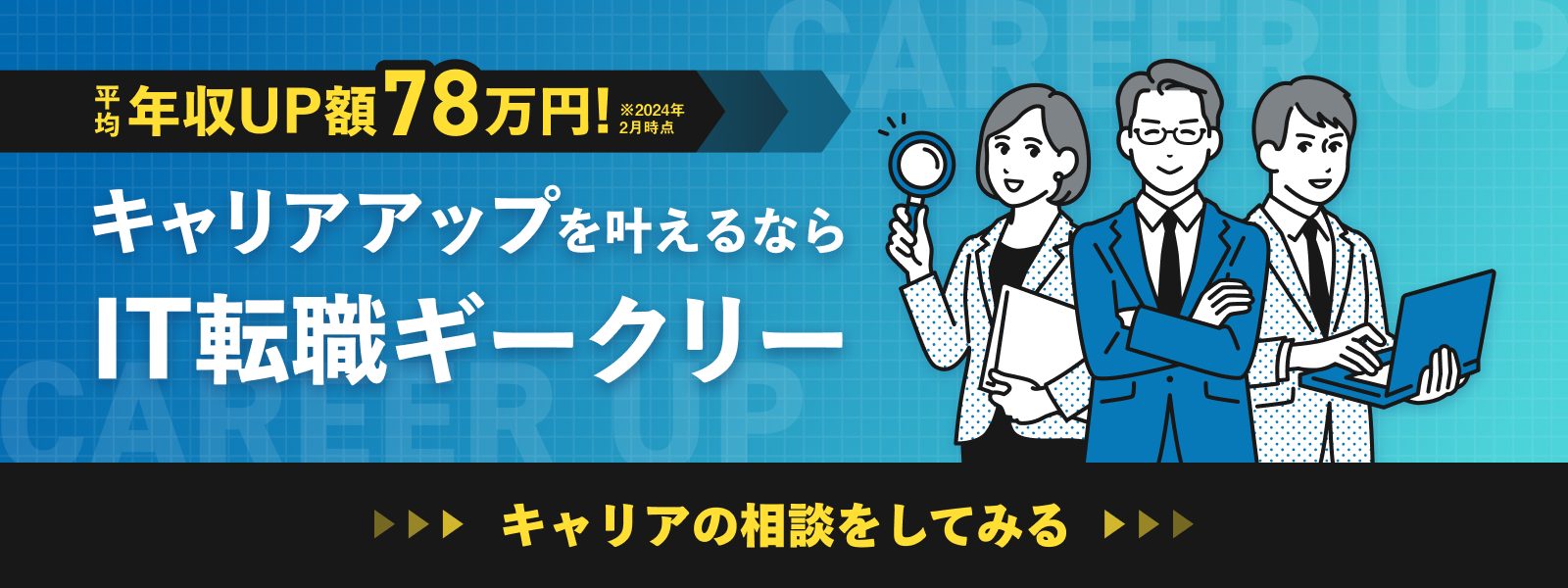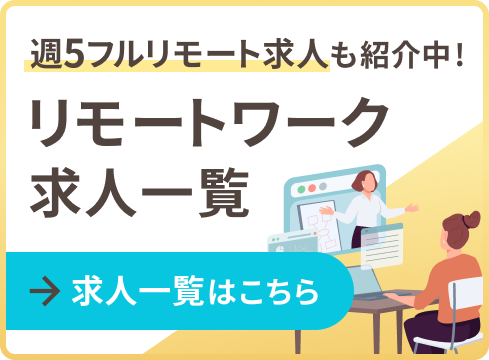今後、ゲーム業界はどうなる?これから求められる人材についても合わせて解説
この記事では、ゲーム業界の現状や今後について、これから転職を考える方向けに解説します。ゲーム業界はグローバル市場も右肩上がりで拡大中です。現在の5つのトレンドや今後の課題、代表企業例、求められる人物像について、転職活動の参考にしてください。
目次
ゲーム業界の現状と動向
ソフト自体の単価と開発費用が上昇している
ゲーム業界の動向として、各ハード本体の機能向上と、それに伴う開発費の高騰が挙げられます。
ハードの機能が向上したことによって、ソフトの開発規模が大きくなり、人件費や開発コストも高騰しました。
以前は5,000万円程度でも開発できていたゲームソフトですが、近年では10億円でも低予算だといわれ、特にAAAと呼ばれるような大手企業が多額の開発費や販売推進費用を費やすソフトには、数百億円もの予算が投じられることもあります。
予算の変化は開発期間の変化でもあり、1年から3年、さらに長期的な期間を要して開発を行うゲームが一般化している点も近年のゲーム業界の動向です。
また、ハードの進化に伴い、ソフトの販売価格も上昇しています。
ゲームの販売形態も変化している
ゲーム業界の市場規模拡大の背景の1つに、販売形態の変化が挙げられるでしょう。
日本では従来、ゲームソフトを貸し借りして遊ぶ習慣があることから、現在でもパッケージ販売は根強い人気があります。
一方、海外ではより利便性を求めダウンロード販売メインに推移しており、ダウンロード専売が約9割を占める現状から、一部特典付きの限定版のようなコレクター向けソフトを残して、日本でも同様に販売形態が変化すると考えられます。
新たなマネジメント職も登場している
開発規模が大きいほど、メンバーの管理者、現場進行の管理者、プロジェクト全体の管理者など、段階的な管理者が必要です。
そのためマネジメント職をマネジメントする役職の重要性が増しており、ゲームの内容や技術的な観点とはまったく別の視点から全体を管理する人材が求められるなど、ゲーム業界の職種はさらに多様化する可能性があります。
また、大規模開発が一般化する一方では、小規模開発でも世界中でヒットする作品も生まれており、ゲーム業界の開発手法は二極化しています。
AAAの対局であるインディーゲーム(インディペンデント・ゲーム)は、少人数・低予算で開発されたゲームであり、代表例はマインクラフトやスイカゲームなどです。
小規模開発が台頭する背景には、ゲームエンジンの普及により開発のハードルが低くなったことが挙げられるでしょう。
(参照:ゲームメーカーズ)
ゲーム業界は今後も右肩上がりでグローバル市場も拡大
国内ゲーム市場規模は、2020年に2兆円を突破して過去最高規模を記録して以降も、高い水準を維持しています。
グローバル市場は、2021年時点で21兆650億円、2030年には95兆3770億円になるという市場予測もあり、引き続き大きく成長を続ける見込みです。
日本市場はまだ1割にも満たない点と、ゲーム市場が世界的に右肩上がりで推移している点から、今後の日本のゲーム業界は伸びしろが期待されています。
【あわせて読みたい】ゲーム会社はやめた方がいい?よく言われるゲーム業界の噂についてはこちら⇓
将来性が高いゲーム業界の求人は「Geekly(ギークリー)」で探してみよう
\ ITエンジニア求人も多数紹介中! /
「自分に合う条件の求人がなかなか見つからない…」
「今のスキルでチャレンジできる求人ってあるの?」
「もっと環境が良い職場で働きたい!」
上記のような大切なキャリアのご相談はぜひ「IT特化の転職エージェント ギークリー」にお任せください!
GeeklyではIT業界や職種を熟知したキャリアアドバイザーがどんなお悩みでもお話を伺い、業界特化の45,000件*以上の豊富な求人情報から、あなたに合った求人をご提案いたします。
(*26年1月時点)
Geeklyを利用して転職成功したKさんの例
- ご年齢:40代
- 企業:受託開発⇒事業会社
- 職種:システムエンジニア⇒Webエンジニア
- 転職回数:1回
- 転職理由:自社のプロダクトに携わりたかった
Q.転職活動においてどのようなことを不安に感じられましたか?
単にどのくらい転職活動に時間をかけないといけないのか見えていなかったという点と、転職活動を考え出した35歳は市場や企業にとって需要があるのかという点です。
Q.転職活動で得られた気づきや考えの変化はありましたか?
転職活動に対しての不安はギークリーで面談して、一瞬で解消されました。面談後の書類の作成も一緒に進めていただいたので、「こんな感じでいいんだ」と不安が払拭されました。
Q.ギークリーで紹介された求人についてはいかがでしたか?
準備していただいた求人は100社以上もありパワフルさを感じたのですが、最初の面談の時に書類を応募する企業数と、そのうち一次面接を通る総定数や内定が出る企業の総定数を出していただいて、それをどのくらいの期間で行うのかという指針があったので、納得感がありました。
【あわせて読みたい】事業会社へ転職に成功したKさんの事例はこちら⇓
Geeklyのサービスご利用の流れ
STEP1:以下のボタンから転職支援サービスにご登録
STEP2:キャリアアドバイザーとのカウンセリング
STEP3:求人のご紹介
STEP4:書類選考/面接
STEP5:入社/入社後フォロー
IT特化の転職エージェントのGeekly(ギークリー)なら、専門職種ならではのお悩みも解決できる専任のキャリアアドバイザーがカウンセリングから入社後まで完全無料で全面サポートいたします!
転職しようか少しでも悩んでいる方は、お気軽に以下のボタンからご相談ください。
\ エンジニアのキャリアに迷ったら! /
ゲーム業界の5つのトレンド
ゲーム業界には多くの変革が訪れており、各企業が次々と新しい試みを発表しています。
ゲーム業界の現状と今後の動向を考えるうえで、外せない5つのトレンドをご紹介します。
- ①次世代ゲーム機の登場
- ②eスポーツ市場の成長
- ③クラウドゲームの市場拡大
- ④サブスクリプション型ゲームの登場
- ⑤巨額投資が行われるVRゲーム
それぞれ見ていきましょう。
①次世代ゲーム機の登場
2024年、家庭用ゲームのハード市場をけん引したのはNintendo Switch、PlayStation 5、Xbox Series X・Sでした。
ロード時間短縮やグラフィック向上などが取り沙汰されていますが、本当の価値はネットサービスの充実にあるでしょう。
特にXbox Seriesとも連携して300以上のタイトルが遊び放題になる「Xbox Game Pass」や、オンラインマルチプレイ・クラウドゲームサービスにも対応した「Xbox Game Pass Ultimate」が注目されています。
両機種とも光学ディスクドライブ有りのタイプと、光学ディスクドライブ無し・ダウンロードコンテンツ専用のタイプが発売されています。
これは、後述のクラウドゲームやサブスクリプション型サービスにゲーム業界の主流が移行していく象徴ではないでしょうか。
また、2025年6月にはNintendo Switch 2の発売が開始しています。同年4月24日以降、順次抽選または予約が行われ大きな話題となりました。
これら次世代ゲーム機が「最後の家庭用ゲーム機になるのでは?」といわれています。
②eスポーツ業界の急成長
財務省によると、2021年の国内eスポーツ市場は78.4億円でした。
世界市場の1,188億円に対し現状は小規模にとどまっているものの、2025年には約180億円まで成長するなどさらに拡大が見込まれることから、今後も期待されている市場です。
2020年にはNTTドコモがeスポーツ業界に参入し、「PUBG MOBILE」のeスポーツリーグ「PUBG MOBILE JAPAN LEAGUE SEASON 1」の運営を開始しました。
また、NTTドコモはRiot Gamesともパートナーシップを結び、2021年には「League of Legends:Wild Rift」を開催しています。
そして、アジアオリンピック評議会(OCA)が主催する国際総合競技大会AIMAG(アジアインドア&マーシャルアーツゲームズ)というイベントでも、eスポーツが正式競技として採用されており、eスポーツは引き続き特に注目の分野でしょう。
(参考:財務省『日本におけるeスポーツの発展のために』)
【あわせて読みたい】eスポーツについて詳しく知りたい方はこちら⇓
③クラウドゲーム市場へは巨大IT企業4社参入
クラウドゲーム市場へは、世界の大手IT企業がすでに参入しています。
- Google:Stadia
- Amazon:Luna
- Facebook:Facebook Gaming
- Microsoft:Xbox Cloud Gaming
アメリカの巨大IT企業GAFAのクラウドゲーム参入は2019年から活発化していました。
2019年11月にGoogleがリリースしたクラウドゲームサービスStadiaをはじめとして、2020年9月に情報公開されたAmazonのLuna、2021年10月より日本公開となったMicrosoftのクラウドゲームサービスXbox Cloud Gamingが代表的です。
この3社に続き、FacebookもFacebookアプリとブラウザでプレイできるクラウドストリーミングゲームを公開しています。
デバイスを選ばずに遊べるクラウドゲームは、今後のゲーム市場の担い手にとしての期待もありますが、現段階では次世代ゲーム機と全く同じパフォーマンスは難しい状況です。
「ストリーミングの遅延」といった問題を5Gで解決できるかどうかが、これからの課題でしょう。
④サブスクリプション型ゲームに注目
Netflixに代表されるサブスクリプション型(=定額課金)サービスも、ゲーム業界に大きく進出しました。
どのサブスクリプション型サービスも、月額500円〜600円ほどで約100以上のゲームを遊び放題となっています。Xbox Games Pass・PlayStation Now・EA Accessの利用者も2020年以降増加傾向です。
モバイルゲーム市場ではApple ArcadeやGoogle Play Passに加えて、Game Clubというスタートアップ企業も参入しています。
しかし一方で、ゲームのサブスクリプション型サービスについては次のような疑問を持つユーザーも少なくありません。
「利用期限に縛られるのが嫌」
「多すぎて遊びきれない」
「ゲームソフトは所有したい」
上記のような意見もあり、今後の動向に注目です。
⑤巨額の投資が行われるVRゲーム
VR元年と言われた2016年から10年ほど経ち、近年では、大手ゲーム企業によるVRゲーム会社の買収や巨額の資金調達が相次いでいます。
スウェーデンのゲーム大手「Thunderfulグループ」は、イギリスのVRゲームスタジオ「Coatsink」を31.5億円で買収しました。「Coatsink」のVRゲーム事業に、さらに89.8億円を投入する見込みです。
「ウォーキングデッド」で有名なVRゲーム開発の「Survios」は、総額75億円もの資金調達をしています。
以前としてVRゲームが秘める大きな可能性は注目されており、2020年のFacebookの「Oculus Quest」発売以降は多くの企業が資本投下を始めています。
【あわせて読みたい】ゲーム業界の職種図鑑はこちら⇓
ゲーム業界の事業構造
ゲーム業界は、いくつかの企業群で構成されています。
・ゲームパブリッシャー
・ハードベンダー
・プラットフォーマー
・ゲームディベロッパー
・スマホゲームパブリッシャー
以下、それぞれ解説します。
ゲームパブリッシャー
ゲームパブリッシャーは自社のIPタイトルをもち、ゲームの販売を行う企業です。
次のような企業が該当します。
・スクウェア・エニックス(ドラゴンクエスト)
・CAPCOM(モンスターハンター)
・セガ(ぷよぷよ)
ゲーム企業として昔から知名度の高い企業の多くはゲームパブリッシャーもしくはハードベンダーに分類されます。
ハードベンダー
ハードベンダーにあたるのは、次のような企業です。
・任天堂(Nintendo Switch)
・SONY(PlayStation)
・マイクロソフト(Xbox)
ゲームパブリッシャーはハードベンダーが提供するゲーム機器に合わせてゲームを開発すると同時に、これらのハードベンダーも自社でゲームソフトを販売しているため、ゲーム業界内でも大きい立ち位置です。
プラットフォーマー
プラットフォーマーには以下が該当します。
・Apple(Apple Store)
・モバゲー(ディー・エヌ・エー)
ゲーム機器メーカーのインターネット版と言い換えられる企業です。
ゲームディベロッパー
ゲームディベロッパーは、ゲームの開発を専門に行う会社です。
例えば「ポケモン」シリーズであれば、販売を行うパブリッシャーは任天堂ですが、開発を行っているのはゲームフリークです。
このゲームフリークがゲームディベロッパーにあたります。
ゲームディベロッパーのなかにも、ゲームの企画から行う企業や、設計書通りに開発だけおこなう企業など、玉石混交です。
スマホゲームパブリッシャー
今やスマホゲームの開発は多くの企業が行っています。
・ガンホー・オンライン・エンターテイメント(パズル&ドラゴンズ)
・ミクシィ(モンスターストライク)
・Cygames(ウマ娘 プリティーダービー)
・コロプラ(白猫プロジェクト)
代表例は上記のとおりです。
その他にもスマホゲームの制作は多くの企業が行っているため、流行したスマホゲームのパブリッシャーを調べてみると自分に向いている企業が見つかるかもしれません。
【あわせて読みたい】ゲーム業界に向いている人の特徴についてはこちら⇓
\ 自分に合う働き方が分かる! /
ゲーム業界の今後の課題
ゲーム業界の課題には、テクノロジーの観点以上に、「これからの時代にどう対応していくか」という部分が多いようです。
・少子化への対策
・海外マーケットでのシェア獲得
・ゲームに対する社会の風潮
・業界のジェンダーレス化
・withコロナ時代の働き方
以下、それぞれ解説します。
少子化への対策
少子化によるマーケット縮小はゲーム業界の大きな課題です。
ゲームを消費する世代は若者が多く、65歳を超えた高齢者がゲームを積極的に楽しむ機会は少ないでしょう。
市場規模を拡大していくには大人を取り込むだけでなく、若年層の多い海外マーケットにアプローチする必要があります。
海外マーケットでのシェア獲得
海外で根強い人気を誇る日本のゲームは多いですが、海外輸出には苦戦しており、世界のゲーム市場での日本のシェアはかつての50%から、今では10%台にまで落ち込んでいます。
その理由は国内と海外での趣味・嗜好の違いです。
RPGやアクションといったジャンルを好み、現実には存在しないキャラクターやファンタジーな世界観に惹かれる日本人に対し、海外の人たちはリアルを求めます。画質や設定においてもリアルさを追求した「FPS」というジャンルが人気です。
これから海外市場でシェアを拡大していくにあたり、日本人と海外の人たち両方に好まれる作品をいかに作るかが課題でしょう。
ゲームに対する社会の風潮
ゲーム業界はソーシャルゲームの課金システムや子どものゲームプレイ時間に対する社会の風潮とも戦わなければなりません。
実際にこの課金システムや、ログインボーナスを得るために生活サイクルをゲームに支配されることに嫌悪感を抱く人も続出しており、最近ではソーシャルゲームを離れる人も出てきているため、将来性が疑問視されています。
新たに登場してきたクラウドゲームやサブスクリプション型サービス、次世代ゲーム機を相手にどこまで戦えるかが課題です。
業界のジェンダーレス化
ゲーマー人口における女性比率は、およそ43%といわれています。
「国際ゲーム業界ジェンダーバランス・スコアカード」の2020年版の調査結果によると、ゲーム業界の経営幹部の大半を男性が占めていることがわかりました。
多くのゲームが男性目線で作られているとも捉えることができます。
筋肉モリモリの男性・スタイルの良いセクシー女性というキャラクターたちは、男性経営陣が生んだステレオタイプなのです。
女性幹部が少ないゲーム業界において、いかに女性消費者を理解し、43%を占める女性ユーザーを満足させられるかは非常に重要です。女性の視点を取り入れた経営戦略もゲーム業界の課題です。
\ IT転職のプロがキャリアもサポート! /
今後のゲーム業界で求められる人材は?
今後、ゲーム業界で求められる人物像として、次のような特徴が挙げられます。
・トレンドや最新技術に興味関心がある人材
・他業界に関する知識や業務経験を持つ人材
・国内だけでなく海外事業にも興味がある人材
・プログラミングやサービス開発に携わった経験のある人材
以下、それぞれ解説します。
トレンドや最新技術に興味関心がある人材
ゲーム業界では、トレンドへの意識が欠かせません。
ストーリーや登場するキャラクター像、衣装、背景などの設定すべてにおいて流行が常に変化しているためです。
技術革新もめまぐるしく、最新技術の情報や市場の動向には常に目を向けている必要があるため、情報収集力に長けた人材が求められています。
新しいものが好きな人や進んで流行を取り入れられる方、冒険心が強く自ら新しい情報を追うことができる方は、ゲーム業界で活躍できるでしょう。
他業界に関する知識や業務経験を持つ人材
ゲーム業界が他のさまざまな業界や世間の風潮などに大きな影響を受けているように、他業界の人材もまたゲーム業界で知識や経験を活かすことができます。
例えば社会や経済の仕組み、生物の骨格や筋肉の動き、歴史、文学、化学や科学など、他領域の知見はゲームに奥行きを持たせるからです。
これまでの経験をゲームの世界に活かそうという考えを持って取り組む方は、独自性を強みにできるでしょう。
国内だけでなく海外事業にも興味がある人材
「世界でヒットする作品に携わりたい」という考えを持った人材が、今後のゲーム業界で重宝されるようになるでしょう。
日本は少子化などの影響で労働人口が減っており、国外の人と連携して進めることが求められる仕事も増えています。
広くコミュニケーションをとるためにも、海外に目を向ける意識は必須です。また会社が海外に事業展開する際に、すでに準備が出来ている人材から割り当てられることも考えられます。
プログラミングやサービス開発に携わった経験のある人材
すでにプログラミングの実務経験やサービス開発の知見がある方は、即戦力になりやくゲーム業界でも需要が高くなるでしょう。
実際に手を動かしてプログラミングを行わない職種であったとしても、プログラミングへの理解があることで業務の幅も広がります。
実務を遂行できる能力を持つ人材の需要は今後さらに高まると考えられているため、プログラミングやサービス開発に携わった経験は積極的にアピールするとよいでしょう。
\ 自分に合う働き方が分かる! /
ゲーム業界で将来性がある職種は?市場価値を上げる方法とは
ゲーム業界での将来性について、以下解説します。
・ゲームアプリ開発に関係する職種
・ゲーム業界のトレンド技術
特にゲーム業界でエンジニアとして活躍したい方は、あらかじめ市場価値を上げる方法としてトレンドの技術についても把握しておきましょう。
ゲームアプリ開発に関係する職種
ゲームアプリ開発には、実は多くの職種が携わっています。
例えばゲームを企画する「ゲームプランナー」、CGやUI/UX、エフェクト、グラフィック、サウンドなどそれぞれの「デザイナー」、ソフトウェア開発、ハードウェア開発などが概要します。
冒頭で述べた通り、業界をけん引するアプリの開発を手掛ける人材への需要は今後も続くでしょう。
ゲームエンジニアに求められるのは、プログラミングスキルに加え、ゲームのエンジンに関する知識です。
また、英語力があると重宝されます。
人気の業界でもあるため、より市場価値の高い人材となるためにはトレンド技術もおさえておく必要があります。
ゲーム業界のトレンド技術
オンラインゲームにおいても仮想通貨が活用されるようになりました。
「Play-to-earn(P2E)」と呼ばれる、ゲーム上で仮想通貨を稼ぎ、さらに現実世界で現金に換金することができるようになる技術です。
これはブロックチェーン技術の応用で、仮想空間「メタバース」では主流になりつつあります。
アプリ市場の活性化に一役買ってでたのが「ポケモンGO®」で、位置情報とAR技術によって新たなゲーム体験を創出したと言えるでしょう。
また、アプリ開発の民営化が進むアメリカでは、ゲームの販売プラットフォームを分散させるストアエコシステムによってゲーム販売所の偏りがなくなるよう進められています。
今後は世界や日本でも、ゲームの新たな配信モデルが誕生するかもしれません。
【合わせて読みたい】20代でゲーム会社への転職方法についてはこちら⇓
\ IT転職のプロがキャリアもサポート! /
ゲーム業界への転職はIT業界特化の転職のプロに相談
新しいテクノロジーとの連携により、ゲーム業界はますます盛り上がっています。
ゲーム業界の現状・動向を見たときに、据え置き型のゲーム機やソフト開発は縮小していくでしょう。反対に、スマートフォン用のゲーム・アプリ開発をしているWeb・モバイル系企業の将来性・可能性はとても大きいと考えられています。
ゲーム業界の中でも伸びていく分野を見極め、ご自身の能力を存分に発揮できる職種への転職を成功させましょう。
「エンジニアとしてゲーム開発に携わりたい」
「IT業界に転職して年収を上げたい!」
「もっと将来性の高い環境で働きたい!」
などのキャリアのお悩みは是非、「IT・Web業界の知見が豊富なキャリアアドバイザー」にご相談ください!
IT特化の転職エージェントのGeekly(ギークリー)なら、専門職種ならではのお悩みも解決できる専任のキャリアアドバイザーがカウンセリングから入社後まで完全無料で全面サポートいたします!
転職しようか少しでも悩んでいる方は、お気軽に以下のボタンからご相談ください。
\ エンジニアのキャリアに迷ったら! /
あわせて読みたい関連記事
新着記事はこちら


 関連リンク
関連リンク