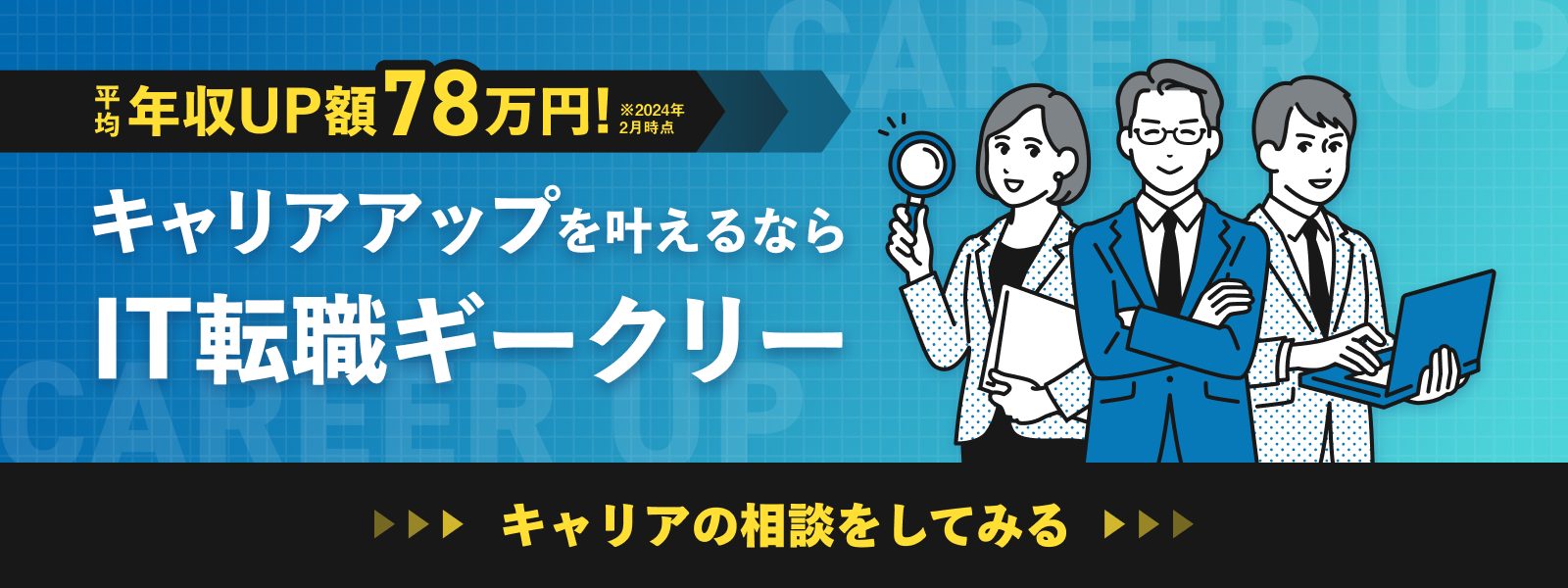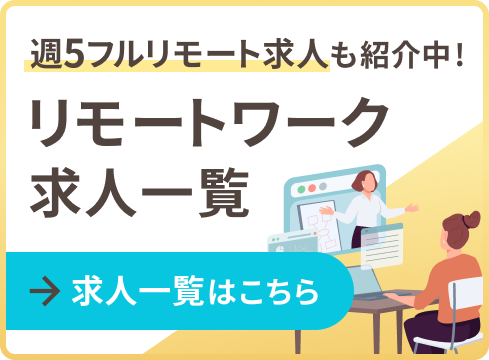SLAとSLOの具体例は?ITサービス用語の意味の違いを解説
サービスレベルの保証という意味の「SLA」と、提供側の目標値という意味の「SLO」は、それぞれの内容と違いを理解しておく必要があります。事例と共に紹介しますので、2つの用語の違いを把握して、契約トラブルを未然に防ぎましょう。また、混同しやすい言葉として「SRE」についても解説します。
目次
SLAとSLOの違い
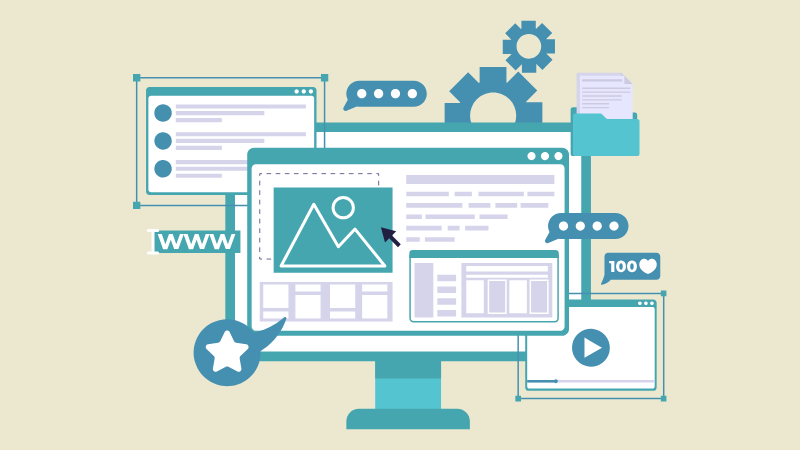
「SLA」と「SLO」は、システム運用サービスに関連するワードとして使われています。
SLAは契約であり、SLOはSLAを結ぶためにより厳しく設定された根拠である点が両者の違いです。
SLAとは、ITサービス提供者がユーザーに対して提示するサービスの品質レベルの保証を指します。
一方SLOは、ITサービス提供者が目標として設定する品質の水準です。
ユーザーは自身が必要としているサーバーやストレージの容量や稼働率をSLOで確認し、満足な内容であれば、SLAのステップに進みます。
SLAを確認し、対象サービスの稼働率や稼働しなかった場合の返金方法など契約の保障を把握してから契約に進むという流れです。
\ エンジニアのキャリアに迷ったら! /
ITサービスのSLAとは?
SLAはサービスの品質に関する取り決め
SLAはService Level Agreement(サービスレベルアグリーメント)の略で、以下のような意味を表します。
・サービス提供を(Service)
・どのレベルで(Level)
・合意するか(Agreement)
このように、SLAはサービス提供者とユーザーとの間で結ばれる、品質に関する契約です。
サービス提供者がどの程の品質のサービスを保証するのか、またそれを達しなかった場合どのような方法で解決するのかなどをユーザーとの間で取り決めを行います。
SLAの要件基準
SLAの要件設定基準は、稼働率やサービスの定義・レベル、またそれに対する返金規約などで記載されていることが一般的です。
ここではそれぞれの要件について解説します。
月間稼働率
月間稼働率は1ヶ月の間にどの程度稼働し続けているかを表しており、システムが停止している時間を差し引いた稼働時間で表示されます。
たとえばSLA99.99%や99.999%のような形で記載されており、月間稼働率の数字が高ければ高いほどシステムの安全性が高く、故障が少ないことが分かります。
サービスの定義
サービスの定義は、この契約によってどのようなサービスを提供するのかという大前提を表しています。
例えば1台のパソコンで使用できるサービスの契約を行いたいというユーザーの希望に対し、契約書には4台分で使用可能なライセンスが含まれているなどの相違があると、ユーザーとサービス提供者の間で意思の合致していないため契約が成立しません。
サービスのレベル
サービスレベルは数値や可視化できるサービスの内容を表しています。
これはSLOにも似ていますが、サービス提供者がサーバーやストレージ、通信速度などどの程度高いサービスを提供するのかを数値で示すものです。
返金規約
返金規約は、他の3項目で設定した基準値や定義を違反又は下回った場合に、どのような形で返金・解約対応を行うのかを定める項目です。 この返金規約が生じるのもSLAの特徴です。
SLAの具体例
SLAの具体例には、以下のようなものがあります。
レスポンス
顧客からサポートの要請があった場合に、どれだけ迅速に対応するかを定めます。
対応時間
「平日の何時から何時までは対応する」というように、対応時間を定めます。
監視と報告
稼働状態を24時間体制で監視する、障害発生時は何分以内に報告するといった時間を定めます。
パフォーマンス
UXの観点で、提供するシステムやアプリケーションのレスポンスなどに関する基準を定めます。
バックアップ
データ復旧やインシデント時の対応のために、バックアップの時間や保存期間を定めます。
\ IT業界・職種の最新情報が満載! /
ITサービスのSLOとは?
SLOはサービスレベルの目標値
SLOはService Level Objective(サービスレベルオブジェクティブ)の略で、以下のような意味を表します。
・サービス提供を(Service)
・どのレベルで(Level)
・目標値として設定するか(Objective)
このように、SLOはSLAで設定された契約内容を履行することを目的とした、サービス提供者側の取り決めです。
サーバーやストレージといった領域の可用性・性能・セキュリティなどの目標値を数値化し、ユーザーに提供することで、ユーザーはどの程度の実用性があるのか理解しやすくなります。
SLOの設定基準
SLOで設定されている目標は企業や業態によってさまざまですが、可用性・セキュリティ・作業手順・サポート体制などの項目で設定されていることが多いです。
可用性
可用性は月間でどの程度稼働することができるのか、またメンテナンスなどでシステムが停止する頻度や、その告知方法などが記載されています。
セキュリティ
セキュリティはサービス提供がどのような形でシステムのセキュリティ制度を高めているか、またどのようなセキュリティ基準に準拠しているかを記載しています。
作業手順
作業手順は、サービスを利用する際にどのような手順で使用することができるのかという説明書の役割を果たしており、初めてサービスを利用する人でも理解できるような形で記載されています。
サポート体制
サポート体制は、ユーザーからの質問やトラブルがあった際にどのような方法でサポートを行うか、またそのサポート時間などについて記載しています。
SLOの具体例
SLOの具体例には、以下のようなものがあります。
可用性
「サービスの月間可用性は99.95%を維持する」など、サービスが正常に作動する割合の具体的な目標設定です。なおこの場合、月間で許容されるダウンタイムは約21分となります。
エラー率
「エラー率2%未満」など、システムやサービスでエラーが発生する割合の目標を指します。ユーザーに影響を与えるエラー頻度を最小限に抑える取り組みが求められます。
レスポンスタイム
「応答時間300ミリ秒以内」など、ユーザーからのリクエストに応答する時間の目標です。パフォーマンスに対する具体的な目標設定の項目です。
インシデント対応
「インシデントの初期対応は15分以内に行う」など、インシデント発生時の対応スピードの目標設定です。
\ エンジニアのキャリアに迷ったら! /
SLIやSREとの違い
SLAやSLOと同様に、SLIやSREもシステム運用サービスに関連するワードです。
以下、SLIとSREについて解説します。
SLIはSLOの達成率を確認するサービスレベル指標
SLIはService Level Indicatorの略で、サービスレベルの指標という意味です。
サービスの稼働状況を数値化し、SLOがどれだけ達成しているかを測定します。
サービスの品質向上や顧客満足度向上を目的として用いられ、指定されたSLOを下回る場合はシステムの可用性を高める施策を講じる必要があります。
SREは信頼性を保つための運用技術
SREはSite Reliability Engineeringの略で、システムの信頼性を保つための運用技術という意味です。
Googleによって確立された概念であり、サービスを改善して最終的にUXを向上させることを目標とします。
システムの信頼性を高めるための取り組みであり、業務の自動化や現場の管理及び運用の負荷とコスト軽減や、問題の早期発見にも繋がっています。
近年SREに特化したSREエンジニアという職種も登場していることから、顧客に対する信頼性向上や運用の効率化が重視されていることがわかるでしょう。
【あわせて読みたい】SREエンジニアについて詳しくはこちら⇓
システムの信頼性を維持する
システムを運用している以上、何らかの形でトラブルが起こってサービスが停止するリスクがあります。 システムの信頼性を確保し、できる限りリスクを低減することはSREの重要な役目の1つです。
具体的には、サーバやネットワークを冗長構成にする、遠隔地のデータセンターにシステムのバックアップを作成するなどが挙げられます。 これは顧客と合意したSLAを守ることに繋がります。実際にパブリッククラウドとして提供されるサービスの中には、複数の施策を組み合わせることで99.9%以上の信頼性を達成しているものもあります。
システムの性能を上げる
運用業務の中では、システムの性能を上げていくこともSREに求められます。
例えば、あるWebアプリケーションの中での画面遷移が5秒以上かかってしまうとユーザーにとっては大きなストレスです。そのため、信頼性以外にもサーバとの通信や画面遷移にかかる時間もSLAとして決められることがあります。
性能を上げるための施策としては、ロードバランサを設置して複数のサーバに負荷を分散する、ネットワークを専用線にして帯域を確保するなどの方法があります。また、設計や開発の段階から性能値を計測してあらかじめ対策を打っておくことが大切です。
システムへの変更・問合せ管理
SREの役割には、システムへの変更や問合せの管理も含まれます。
例えば、システムで使っているソフトウェアのバージョンやパッチの情報は日々変わるため、随時更新記録を残す必要があります。 また、ユーザーからの問合せについても、受付から解決までの状況管理が必要です。
これらの作業をExcel台帳への記録など人手に頼った方法で実施していると効率化は進みません。 さらに、ヒューマンエラーによるミスが発生してしまう可能性もあります。SREには適切なツールや方法論を使って、効率的かつ正確な運用フローを確立することが求められます。
\ エンジニアのキャリアに迷ったら! /
クラウドサービスのSLA比較
有名なクラウドサービスには次の4社が挙げられます。
・AWS(Amazon Web Service)
・Microsoft Azure
・GCP(Google Cloud Platform)
・OCI(Oracle Cloud Infrastructure)
いずれも99.95%から99.99%と、サービスの可用性の高さに大きな違いはありませんが、AWSとGCPは99.99%以上の高い可用性を実現できるサービスが多いです。
4社の違いとして、SLAに関する返金対応について解説します。
返金対応の違い
AWS、Azure、GCP、OCIのいずれも、返金方式はプロバイダで「サービスクレジット」として提供される点で共通しています。
現金による返金は行われません。
返金の条件として、AWS、Azure、GCPでは可用性を基準として下回った場合に返金対応となることが一般的ですが、OCIはSLA違反を基準とします。
また、請求方法はいずれもサポートリクエストを通じて行いますが、Azureでは自動的にサービスクレジットが発行されるケースもあるようです。
返金対応は各社で類似しているものの、請求方法や条件はそれぞれ細かく設定されているため、契約時にSLAと返金ポリシーをしっかりと確認しましょう。
また、サービスの基準値を下回るような場合は、自主的に請求申請することが大切です。
\ エンジニアのキャリアに迷ったら! /
契約前にSLAとSLOの確認は必須
サービス契約前には、SLAとSLOは必ず確認しましょう。
サービスの内容やその根拠、そして基準値を下回った場合の返金の規約などの確認も必須です。
また、サービスを発注する側でなく受ける側としてエンジニアのスキルを活かしたい方は、転職エージェントに相談して自分に合う仕事を見つけましょう。
「エンジニアとして上流工程に携わりたい」
「IT業界に転職して年収を上げたい!」
「もっとモダンな環境で働きたい!」
などのキャリアのお悩みは是非、「IT・Web業界の知見が豊富なキャリアアドバイザー」にご相談ください!
IT特化の転職エージェントのGeekly(ギークリー)なら、専門職種ならではのお悩みも解決できる専任のキャリアアドバイザーがカウンセリングから入社後まで完全無料で全面サポートいたします!
転職しようか少しでも悩んでいる方は、お気軽に以下のボタンからご相談ください。
\ エンジニアのキャリアに迷ったら! /
あわせて読みたい関連記事
新着記事はこちら


 関連リンク
関連リンク